Human's voice 技術者たちの熱き想い

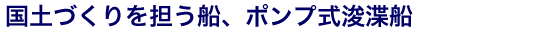


昭和40年代を頂点に、国土づくりに華々しい活躍をみせてきた海上作業基地がある。「ポンプ式浚渫船」だ。時代は変わっても、浚渫、埋立の役割はまったく変わりなく、国内外の至る所でいまも稼働する。そして、ポンプ式浚渫船とプロジェクトの数だけ、そこに関わった海の男達のドラマがある。
ポンプ式浚渫船の船長は、特殊技能の持ち主
ポンプ式浚渫船とは、海底の土砂をカッターで掘削し、それをポンプで吸い上げ、目的地まで排送する船のことである。浚渫埋立など海洋工事を手がける企業にとってはなくてはならない作業船で、これまで国内外の多くの国土づくりに貢献してきた。
船は、海底を掘削するカッターや吸い上げた土砂を埋立地などに送る一連の運転・管理などを担当する「甲板部」と、船のポンプやエンジンの運転を維持・管理する「機関部」の2部門がある。機動部隊といえる甲板部は、海底で回転するカッターに異常があったり、排砂管にトラブルがあった場合に、迅速に対応する機動力が求められる部門だ。一方の機関部は、いわば縁の下の力持ち的な存在。船のエンジンやポンプなどを稼働させ、作業が円滑に進むように緻密で柔軟な管理が求められる。そしてこれら全体の管理をするのがブリッジである。
村川は現在、北海道苫小牧港の浚渫工事で、「第三亜細亜丸」の指導船長として数十人のスタッフを指揮する。大型で設備が複雑に配置された浚渫船で、甲板部と機関部を掌握し、さまざまな状況を瞬時に判断する能力が求められる立場だ。
それゆえにポンプ式浚渫船の船長は「きわめて高度な特殊技能の持ち主」といわれる。
村川が船長として最も大切にするのは「チームワークと統制」である。「あらゆる判断は船長に一任されます。浚渫船は海上の作業基地、すなわち海に浮かぶ工場のようなもので、チームワークと統制がなによりも大切になります」と強調する。1人が突っ走ると、致命的な事故につながりかねない。チームワークと統制は、誰も助けてくれない海の上の仕事を通して多くの修羅場を乗り切ってきた村川が得た教訓である。
見えない世界で、自在に手足を操る
極めて高度な特殊技能といわれる船長の能力とは、一言でいえば「巨大な船を、まるで自分の体のように自在に動かす技能」だ。同時併行した複合的な仕事。言葉でいうほど簡単ではない。なんといっても、作業場所は標識も何もない海の上であり、浚渫するポイントは、目では見えない海底だからやっかいだ。
海底には、土砂だけではなく多くの障害物がある。第二次大戦時の不発弾がみつかることも決してまれではないほど危険が伴う仕事だ。事前の調査が不可欠で、突発的な障害物への素早い対応が重要で工程に大きく影響する。それに地盤の硬さに応じて、カッターにかかる負担を軽減するバランス調整も微妙な作業だ。それでも村川は巨大な船を自分の手足のように自在に操っていく。浚渫場所の深度に合わせて上下するラダー、ラダー先端にあり土砂を掘削するカッター、土砂を吸い込み目的地まで送泥するポンプ設備などの船の装備は自らの身体の一部のようだ。
しかもカッターは一カ所で作業するのではなく、「ちょうど車のワイパーのようにスイングさせる」必要がある。そのためにはワイヤを交互に引っ張り、船の向きを変えていく。しかも、「スイングさせたうえで前進させなければ当然ながら浚渫は進みません」。そのためのスパッドと呼ばれる装置の操作も重要なカギを握る。加えてポンプ式浚渫船の転錨をするための揚錨船も船長の指揮下になるから「休む暇もない」ほどだ。
ラダーの角度を常に掘削深度に一定に保ち、正確な浚渫作業をするのは、「船長としての最大の腕の見せ所」である。甲板部や機関部と連携しながら、さまざまな情報をもとに同時並行的に指揮していく。その複合的な作業は、まさにマルチな特殊技能と呼ぶにふさわしい。作業ロボットともいえるポンプ式浚渫船を自分の体として一体化して初めて、効率的な浚渫は可能になるのである。
灼熱地獄に人相が変わった

村川がこの世界に入ったのは、昭和44年のこと。高度成長の波に乗って、日本の浚渫が頂点へと向う、まさにもっとも輝いていた時代である。北海道の小さな港町に生まれた村川の夢は、「海に関係した仕事につくこと」。その夢をかなえさせてくれる仕事が浚渫だった。
中東における先駆けとなる重要な工事を経験する幸運に恵まれた。昭和48年、石油積出港の桟橋の浚渫で赴任する。言葉もなかなか通じず文化・風習も異なる地での仕事。「正直たいへんでしたね」(笑)。なんども技術的な問題に見舞われたが、村川は「技術面には自信があったし、辛いと思うこともありませんでした」と振り返る。「辛いと思う前に体を動かして解決するタイプ」という性格が心を軽くした。
だが、別の所で想像を超える苦難に直面した。暑さとの戦いである。北海道生まれの村川にとって、「気温が40℃以上にもなる灼熱の世界」は地獄に等しかった。日中は現地の作業員さえ働かない。そんな炎天下で懸命に働いた。「赴任した20人近い技術者たちの体重は一気に10Kg以上も落ちて人相が変わりましたね」。一時帰国した際、あまりの痩せ方に周囲は愕然とし、言葉を失ったほどだ。だがその後も中東でのさまざまなプロジェクトを成功に導いた。
現在、指揮する北海道苫小牧港の浚渫工事では、大型台風の直撃も経験した。近くに避難場所がみつからず、現地で必死に耐えた。「絶対に乗り切ってやる」という強い意志と「絶対に乗組員を危険な目に遭わせない」ことを心に誓って耐えた。知識と経験、それに強靱な精神力に裏付けられた判断力。これらがぎりぎりでの決断を確かなものにした。数々の体験が、やがて村川をわが国屈指のポンプ式浚渫船の船長に押し上げていく。
船長として絶対に譲れないものがある
村川にすれば、マルチな特殊技能は確かに重要だが、船長としては「必要十分」な能力ではなく、「必要最低限」の能力と捉えているようだ。決断力、行動力、指導力、統制力など、技術・技能以外の部分を大切にする。
船長として決断すれば、たとえ会社上層部がなんといってきても、絶対に譲らない。そんな気概をもち続けてきた。
天候が悪く作業はできないと判断したことがあった。ところが会社側としては、工程が狂うので何とか作業できないかと打診してきた。工程を全うしたい、ロスは防ぎたい。会社側のそんな気持ちは船長としてもよくわかっていた。だが「俺は大事な部下の命を預かっている。だから危険に遭わせることは絶対にできない」と信念を曲げなかった。
「船のことはすべて最高責任者である船長に委ねる」。最終的には船長の気持ちを理解し尊重してくれる風土が会社にはあった。「ありがたいこと」と村川は感謝する。
指導船長となった村川はいま、これまで培った技術・技能を後進に伝えることに情熱を傾ける。「仕事は確実に覚えろ」「投げやりになるな」。こう厳しく指導する。かつて自らがこの世界に入った頃は職人的な世界だった。「オヤジ(船長)から『あれをやって来い』と指示され、終わって報告すると『バカ野郎。1つ言われたら2つ3つ覚えて来い!』って怒鳴られたものでした」と笑う。さすがに今はそんな指導はしないというが、「『1つのことをやるにしてもいろいろと考えてみろ』というようにしています」と気を遣う。
「長い歴史のなかで培われたわが国の浚渫技術を何とか伝えたい。そのために貢献したい」。多くの困難を克服してきた船長の言葉には崇高ささえ漂っている。
海の工場ともいえる作業船の代表格−ポンプ式浚渫船
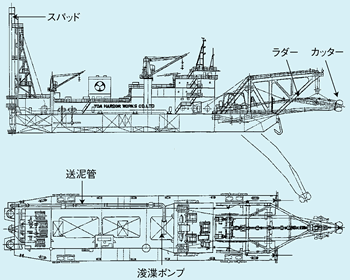
海底を掘って土砂を岸辺に圧送して埋立てる—。ポンプ式浚渫船は、埋立工事に欠かせない船として、日本ではとくに高度成長期に大活躍した。今日でも海外を含め至るところで稼働する。
ポンプ式浚渫船にある設備・装置は、海底の土砂を吸い上げる吸入管、その先端の掘削装置、動力源のポンプ、土砂を圧送するパイプなど。自分で航行するためのスクリューがないのが大半で、船というより浮かぶ作業基地ということもできる。
船の先端にはラダーがあり、ここに土砂を吸い上げる吸入管、さらに先端にはカッターが取り付けられている。このカッターをモーターで回転させながら海底を左右にスイングさせて土砂を掘削、こうしてできた泥水を主ポンプで吸い込み目的地までパイプで送泥するというのがポンプ式浚渫船の役割だ。ポンプの馬力などに大小はあっても、機能的にはほぼ同じである。
また船尾には船をスイングさせるための扇の要(基点)となるスパッドが2本設置されている。片方のスパッドを海底に打ち込み、船から張り出したワイヤーをウインチで巻き込み船をスイングさせて掘削作業を行う。所定の掘削が終わったら今度はもう一方のスパッドを打ちかえて前進作業に移る。
苫小牧港で活躍する第三亜細亜丸は、長さ78m、幅19.5m、深さ5.5m(吃水4.1m)、排水量6,000tの大型船。主ポンプ8,000psにより1時間当たり1,200㎥の浚渫能力(最大浚渫深さ30m)をもつポンプ式浚渫船で、4,000mの距離を排送可能だ。
第三亜細亜丸による苫小牧港での浚渫工事では、空気圧力により土砂を長距離搬送する新技術も採用されている。