『海紀行』人とまちを支える港を訪ねて

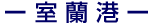

市民が集い、憩うことのできる室蘭港
こうした港の活性化、港まちづくりを一朝一夕で実現することは難しい。最初は函館や小樽のような観光誘導型のウォーターフロントを想い描いていた白川さんも最近は考えが少々変わってきた。「今できることからコツコツと進めたいと思っています。その結果、人間本来のスピードで考え、暮らすことのできる港町を創る。そこに本当の豊かさがあるのではないかと思います」。物理的に恵まれていることばかりが豊かさではないことに気付いてきたという。
観光目的もさることながら、まず市民のための港を創造することが先決である点にも魚住所長は共感する。「中央ふ頭や白鳥大橋周辺の緑地整備も進み、市民と港の距離はどんどん近づきつつあります。個人的にも3号倉庫前の緑地や周辺の船溜りの佇まいに触れるとホッとするんですよ」と目を細める。
室蘭港は基本的に産業港と位置付けられる。港区のほとんどが企業の専用ふ頭であることから人々が集い、憩うことは難しい面があることも事実だ。しかし「羅針盤」の活動、親水施設や緑地の整備によって港を訪れる市民が増え、港に対する関心も高まっている。港まちづくりの成果は着実に現れつつある。
室蘭港には行政とNPOが「協働」する理想形が芽生えている。港町で育ち、暮らす人々が港に元気を取り戻し、町を再生しようとする動きから始まった「羅針盤」。その活動が評価され、今年5月には、港湾に関する優れた企画に贈られる日本港湾協会企画賞が授与された。「今度は自分たちが港に、町に元気をお返しする番なんです」と白川さんは胸を張った。

北海道開発局 室蘭開発建設部
室蘭港湾事務所 魚住 聡 所長

同時に2隻の接岸、荷役が可能なフェリーふ頭

工場群の夜景も室蘭を象徴する風景だ

水深−14mのバースを持つ崎守ふ頭には大型のガントリークレーンも整備された

祝津ふ頭でも親水施設の整備が進む

晴れた日には下北半島も眺望できる地球岬
写真/西山芳一
COLUMN
海上に浮かぶ防災基地 浮体式防災施設(防災フロート)
昨年11月4日、多くの市民が見守る中、室蘭港の函館どっく(株)室蘭製作所乾ドックに巨大な鋼鉄製の箱が浮上した。浮体式防災施設(防災フロート)の進水式だ。海と乾ドックを仕切る扉の下部にある直径80cmの2基のバルブからごう音とともに海水が流れ込み、防災フロートが浮かびはじめると市民からも歓声があがった。
全長80m、全幅24m、高さ4m、総重量1,300tの防災フロートは、通常時は室蘭港西1号ふ頭に係留され係船等に活用されるが、地震などの災害発生時には、救援物資の受入れや、被災者の避難用桟橋といった防災基地として活躍する。防災フロートは浮体式であるため、波や風による揺れや移動量が多く、荒天時の利用には適さないという弱点があるものの、潮位の変化に追従し、係留された船との段差が解消されることから荷役作業が容易に行えるという大きな利点がある。そのため災害時には岸壁を離れ被災地へ曳航し、復旧支援施設として活用することも可能だ。防災フロートは平成7年の阪神・淡路大震災の教訓を活かし、これまで東京湾、伊勢湾、大阪湾に設置されてきた。港湾は大きな災害時に物資の供給拠点として大きな役割を果たす。阪神・淡路大震災の際も、復興は神戸の港から始まったといっても過言ではないだろう。室蘭港の防災フロートも平成12年の有珠山噴火を受け、活火山が至近距離にあり、本州との定期航路が就航するなど、地理的条件や港湾の利便性から配備が決定された。室蘭港では、耐震強化岸壁の整備と合わせ、災害に強い港づくりが進められている。




